「法人携帯を導入したいけど、稟議を通すのが大変…」
「提案書って何を書けばいいの?」
そんな悩みを抱えていませんか?
この記事では、法人携帯の導入を検討している中小企業の方に向けて、社内でスムーズに稟議を通すための提案書テンプレートをご紹介します。
社内を説得するために押さえるべきメリットや反対意見の切り返し方、費用の見せ方まで、実務でそのまま使える具体例をたっぷり掲載。
この記事を読めば、もう提案書で迷うことはありません。
法人携帯の導入を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
法人携帯の稟議を通すために必要な社内提案書の作り方
法人携帯の稟議を通すために必要な社内提案書の作り方について解説します。
それでは順に見ていきましょう。
①提案書に必須の5つの構成要素
法人携帯の導入を稟議にかける際、説得力のある社内提案書を作るには、「構成」が何より大事です。
というのも、読み手は基本的に「結論が先」「根拠が明確」「コストと効果が数字で見える」を重視するからなんですよね。
具体的に、提案書に盛り込むべき構成要素は以下の5つです。
| 構成要素 | 説明 |
|---|---|
| ①背景と目的 | なぜ導入を検討しているのか。現状の課題やニーズを明記する。 |
| ②導入のメリット | コスト削減・業務効率化・セキュリティ強化などの利点を説明。 |
| ③費用と見積もり | 初期費用・月額料金・運用コストの具体的数字と見積元の信頼性。 |
| ④導入スケジュール | いつから、どのように進めるのか。明確な工程が信頼につながる。 |
| ⑤リスクと対応策 | よくある懸念(運用負荷・トラブル時)とその回避方法を記述。 |
この5項目が入っていれば、意思決定者にも「なるほど、考えられてるな」と思ってもらえます。
1つでも抜けてしまうと、「結局何が言いたいの?」と判断保留になりやすいので注意してくださいね。
②意思決定者が気にする3つの視点とは?
社内提案書を作成するうえで忘れちゃいけないのが、「読み手の視点」です。
法人携帯のような設備投資に関して、決裁権を持つ人が重視するのは以下の3点です。
- ①コストとリターン(費用対効果)
- ②リスクとその備え
- ③導入後の運用・管理負担
この3つを踏まえて、提案内容を補強しておくと安心です。
例えば「コストとリターン」については、導入前後でどれだけ経費が削減されるのか、何時間の業務効率化が見込めるのかを数字で示しましょう。
また「管理負担が増えるのでは?」という疑念には、MDM(モバイル端末管理)システムなどの導入をセットで提案すると、かなり説得力が増しますよ。
相手が気にしているポイントに“先回りして答える”提案書が、稟議に強いんです。
③よくあるNG提案書のパターン
法人携帯の導入提案でありがちな失敗パターン、実はけっこうあります。
代表的なのが、「導入ありきで話を進めている」「現状課題が曖昧」「数字が弱い」です。
たとえば、「最近の企業はみんな法人携帯を導入しています」などの抽象的な言い方はNG。
「当社では私用スマホの業務利用が6割。セキュリティリスクが顕在化しており、実際に◯件の情報漏洩リスクが報告されています」など、具体的な背景や課題から話を始めるのが基本です。
また、見積もりだけ貼り付けて「これでお願いします」では不十分。
コストと効果の比較、なぜその会社・プランがベストなのかまで含めないと、「ちゃんと考えたの?」と思われてしまいますからね。
④成功率を高める提案書テンプレート例
最後に、社内提案書をつくる際に便利なテンプレートの一例をご紹介します。
このテンプレートを使えば、要点を押さえた提案書がスムーズに作成できますよ。
| セクション | 記入例 |
|---|---|
| 件名 | 法人携帯導入のご提案 |
| 背景と課題 | 現在、従業員の約6割が個人スマホで業務連絡を行っており、情報漏洩リスクが高まっている。 |
| 導入目的 | セキュリティの強化および業務効率の改善。 |
| 導入効果 | MDM導入で遠隔ロック可能、月間〇時間の業務時間短縮見込み。 |
| 費用 | 月額〇円×〇台、初期費用〇円。3社比較のうち最安。 |
| 導入スケジュール | 2025年7月中に導入、8月より運用開始予定。 |
このようにテンプレートを活用すれば、見落としを防ぎつつ、要点が端的に伝わる資料になります。
資料の「見せ方」も説得力に影響しますので、デザインやレイアウトも意識してくださいね。
法人携帯を導入するメリットを明確に伝える方法
法人携帯を導入するメリットを明確に伝える方法について解説します。
それでは、順に見ていきましょう。
①業務効率化と生産性アップの効果
法人携帯を導入する一番のメリットは、なんといっても業務の効率化です。
例えば、営業職の方が毎回会社に戻ってパソコンで報告書を書くのではなく、外出先から法人スマホで完了できるようになります。
メールやチャット、スケジューラー、CRMツールもすべてスマホ1台に集約することで、移動時間がそのまま“仕事時間”になります。
実際にある中小企業の導入事例では、「営業報告にかかる時間が月10時間削減できた」という結果もあります。
また、業務専用端末があることで、私用スマホとの切り替えがなくなり、集中力や切り替え意識も向上します。
こういった定性的な効果も、稟議で伝えるときに強いポイントになりますよ。
「従業員が“いつでもどこでも働ける”環境を整えること」が、法人携帯の最大の価値ともいえますね。
②経費削減につながる料金プランの最適化
「法人携帯=コストがかかる」と思われがちですが、実は個人利用の精算制度やBYODよりも、トータルでは安くなるケースが多いんです。
理由は2つあります。
まず、法人向けには通話・データ通信がセットになった“ビジネス向け割引プラン”が用意されていること。
1回線あたり月額1,000円台〜3,000円台の範囲で使えるケースが多く、個人契約と比べて非常に安価です。
さらに、通信料を一括請求・一括管理できるため、経理処理もシンプルになります。
社員に通話代や通信費を個別に精算していた場合、そのチェック・計算・振込処理だけで月何時間もかかっていた…という話もよく聞きます。
法人携帯ならそうした“管理コスト”の削減にもつながりますよ。
コストに敏感な上層部には、「月額コストだけでなく、運用・管理にかかる人的コストも減らせます」と伝えると納得されやすいです。
③社員の情報漏えい対策・セキュリティ面の強化
セキュリティ面は、法人携帯を提案するうえで非常に強力な武器になります。
今や情報漏えいの8割以上が「ヒューマンエラー」によるものであり、中でもスマホの紛失・盗難は常に上位にランクインしています。
個人のスマホで業務メールや顧客情報を扱っていた場合、万が一その端末を落としただけで、大きな損害になりかねません。
法人携帯なら、管理者が遠隔でロック・データ消去を行えるMDM(モバイルデバイス管理)が標準で使えます。
加えて、業務に必要なアプリだけをインストール制限する機能もあるので、「SNSや不要なアプリで遊んでいる」といったリスクも減らせます。
また、法人携帯では「セキュリティパッチ適用」や「OSアップデートの管理」なども一括で行えるため、全社的なセキュリティレベルも底上げできます。
「情報漏えい対策を考えたとき、法人携帯は必須のインフラです」と自信を持って伝えて大丈夫ですよ。
④BYODとの違いと法人携帯の優位性
最近では、個人スマホを業務に使う「BYOD(Bring Your Own Device)」も注目されていますよね。
ただ、実際にはBYODには多くの課題があることも事実です。
たとえば、端末ごとのセキュリティレベルがバラバラだったり、業務利用にかかった通信料の線引きが難しかったりします。
また、私用スマホへの業務アプリ導入や、社内情報の保存を嫌がる社員も少なくありません。
その点、法人携帯は「会社が提供した端末」という立ち位置なので、社員にも安心して渡せますし、トラブルも減ります。
稟議で「BYODで十分では?」と突っ込まれた場合は、「運用ルールの統一性・セキュリティ管理の簡易性・社員満足度の維持」の3つを根拠に反論しましょう。
特にコンプライアンスや情報管理が厳しくなっている昨今では、法人携帯の方が圧倒的にリスクが少ないです。
社内で反対されがちな理由とその切り返し方
社内で反対されがちな理由とその切り返し方について解説します。
それでは順に見ていきましょう。
①「コストが高い」にどう対応する?
法人携帯を導入しようとすると、まず最初に出てくるのが「コスト高では?」という声です。
確かに導入初期には端末購入や通信契約など、ある程度の出費は伴います。
ですが、その“コスト”は本当に高いのでしょうか?
実際は、私用スマホの通話代を会社が負担していたり、精算処理に毎月多くの人件費がかかっているケースがほとんどです。
法人携帯にすれば、まとめて安くなったうえで、管理工数も減らせます。
また、「一括見積サービス」などを活用すれば、3社比較などで最安プランを簡単に提示できますよ。
提案書に“費用の見える化”をして、「コスト=投資」であることをしっかり伝えましょう。
②「使いこなせないかも」にどう反論する?
次にありがちなのが、「スマホを使い慣れてない社員が多いから…」という声です。
特に年配の社員や、営業以外の部署ではこの意見が出やすいんですよね。
でもご安心を。
法人携帯は基本的に「最低限の機能だけ使えればOK」な設計にすることが可能です。
アプリも用途を限定し、通話・メール・スケジューラー程度に絞れば、スマホ初心者でも使いこなせます。
加えて、管理部門で「使い方マニュアル」や「初期セットアップ済みの端末」を渡す運用にすれば、利用開始のハードルも一気に下がりますよ。
「使えないかもしれない」ではなく、「使えるような設計をしてあげる」がポイントですね。
③「今のままで問題ない」と言われたら?
変化を嫌うタイプの上司や経営者からは、「現状で問題ない」「困っていない」と返されることもあります。
この場合の切り返し方は、「潜在リスク」を提示することです。
たとえば、「私用スマホでの業務連絡が常態化しており、個人端末に顧客データが保存されている可能性があります」など、今は“見えていないだけの問題”を指摘しましょう。
さらに、「万が一の情報漏えいが起きた場合、取引先からの信頼を失うだけでなく、場合によっては賠償リスクにもつながる」といった“具体的な損害”を示すと、説得力が増します。
人は「得をする」より「損を回避する」方が動機付けとして強いので、この視点は大事ですよ。
④現場と経営層、それぞれへの説得ポイント
社内で提案を通すには、「現場」と「経営層」、それぞれの関心ポイントを押さえておくことが必要です。
現場にとってのメリットは、「使いやすさ」「業務の楽さ」「サポート体制」など。
経営層にとっては、「コストパフォーマンス」「業務効率」「情報漏えい対策」など、数字やリスク管理に関わる部分が重要です。
つまり、提案書や口頭説明の中で、両者それぞれに響くワードを使い分けることがカギなんですね。
例えば、現場には「操作マニュアルも完備していて安心」と伝えつつ、経営層には「〇万円の経費削減が可能で、MDM導入によりセキュリティ向上」と数値でアピールする、といった具合です。
1枚の提案書の中でも「現場目線」と「経営目線」の両方を意識した構成にすると、稟議通過率はグッと上がりますよ。
提案書に使える!法人携帯の比較ポイントと選定基準
提案書に使える!法人携帯の比較ポイントと選定基準について解説します。
それでは、順に見ていきましょう。
①キャリア別の法人プラン比較表
法人携帯を提案する際、決裁者に響くのはやっぱり「具体的な比較」です。
以下に、主要3キャリアの代表的な法人向けプランをまとめました。
| キャリア | プラン名 | 月額料金(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | ビジネスプレミアプラン | 2,728円~ | 通話かけ放題・大容量通信、セキュリティオプション充実 |
| ソフトバンク | スマホ法人基本パック | 2,178円~ | MDM、管理ポータル付きで導入簡単 |
| KDDI(au) | 法人向けスマートバリュー | 2,090円~ | セット割引やカスタマイズ性が高い |
このように、コストだけでなく「サポート内容」や「管理ツール」なども含めて比較するのがポイントです。
提案書では、この表をそのまま貼っても効果的ですよ。
②端末選定時に見るべき4つの観点
法人携帯の導入で見落としがちなのが、「端末」の選び方。
ただ安いものを選べばいいわけではありません。
以下の4つの観点で評価するのがおすすめです。
- ① 耐久性(落下に強い、バッテリー持ちが良いなど)
- ② 管理のしやすさ(OSの統一性、遠隔制御のしやすさ)
- ③ 社員の使いやすさ(サイズ感、操作性)
- ④ コストバランス(端末代と通信費の合計で見る)
たとえば、営業が外回りで使う場合は「防水・防塵・長持ちバッテリー」が優先されます。
事務スタッフが主に社内で使うなら、そこまでハイスペックでなくて大丈夫ですよね。
使用シーンに合わせて最適な機種を選び、それを提案書で説明すると説得力がぐっと増します。
③一括見積サービス「一括.jp」の活用方法
提案書作成にかかる工数をぐっと減らせるのが「一括.jp」のような見積比較サービスです。
これは、必要条件を入力するだけで複数の携帯会社や代理店から最適な見積もりをまとめて取得できる便利なツールです。
例えば、「法人携帯 10台 導入予定」「月額予算3,000円以内」など条件を入力するだけで、条件に合った事業者からの見積が届きます。
その中から「最安」「管理機能が優れている」「セキュリティ対応が万全」など、導入目的に沿った会社を選ぶことができます。
提案書には、「一括.jpを利用して比較・選定した結果」と記載することで、納得感と客観性が出せますよ。
無料で利用できるのも大きなメリットですね。
④料金と機能を踏まえた提案書用の比較資料例
最終的な提案書に載せる資料は、情報を“見える化”して意思決定をしやすくする役割があります。
そこで、以下のような表を作るととても効果的です。
| 比較項目 | プランA | プランB | プランC |
|---|---|---|---|
| 月額料金(1台あたり) | 2,728円 | 2,090円 | 2,178円 |
| MDM管理 | あり | あり | なし |
| セキュリティ対策 | ウイルス対策+リモートロック | リモートロックのみ | なし |
| おすすめ部門 | 全社導入向け | 営業部門向け | 試験導入向け |
このように機能や価格を並べて記載することで、「検討の結果、これが最適」と説明しやすくなります。
経営層にとっては「判断材料の整理」が重要なので、こういった比較資料は必須といってもいいですね。
そのまま使える!法人携帯導入の社内提案書テンプレート
そのまま使える!法人携帯導入の社内提案書テンプレートについて解説します。
それでは順にテンプレートの各パートを解説していきます。
①提案の背景と目的の書き方
提案書の冒頭では、「なぜ法人携帯を導入するのか?」を明確に記すことが大切です。
よくある失敗は、「法人携帯が便利だから導入したいです」と目的が抽象的なこと。
背景としては、現状の業務課題やセキュリティリスク、社員の声など、具体的なデータや現場の実態を入れると効果的です。
以下のように記述してみてください。
【背景】 現在、営業職の約7割が私用スマートフォンを業務に使用しており、情報漏えいリスクおよび通信費精算の煩雑さが課題となっている。 業務連絡がLINEなどの私的チャットで行われることもあり、コンプライアンス上の懸念がある。 【目的】 法人携帯を導入し、業務端末を一本化することで情報漏えいリスクの低減と業務効率化、経理処理の簡素化を図る。
目的の部分は、提案全体を通じて一貫した軸になるのでしっかり書きましょうね。
②導入メリットと期待効果の伝え方
ここでは、導入することでどんな良いことがあるのか?を数字や定量的データを交えて示します。
ポイントは、「現場にとってのメリット」と「会社全体にとっての効果」の両方を記載すること。
【導入メリット】 ・個人携帯利用による情報漏えいリスクを大幅に軽減 ・法人割引プラン適用により、通信費を年間約15万円削減見込み ・営業報告・スケジュール共有等の効率化により、月10時間の工数削減を想定 ・MDM導入により、端末管理の一元化が可能に
「この導入で会社が“得する”」という印象を与えることが大切ですよ。
③費用と見積もり根拠の提示方法
稟議を通すうえで必須なのが「費用の透明性と妥当性」です。
金額だけでなく、どの業者に依頼したか、何社比較したかも書きましょう。
【導入費用(10台の場合)】 ・端末代金(1台):19,800円 × 10台 = 198,000円 ・月額料金(通信+MDM):2,500円 × 10台 = 25,000円/月 ・年間想定運用コスト:300,000円(税別) 【見積元】 ・一括見積サービス「一括.jp」を利用し、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社比較を実施。 ・最もコストパフォーマンスの高いA社を選定。
「ちゃんと比較検討したんだな」と思ってもらえる構成がベストです。
④スケジュールと導入後の運用体制の例
最後に、導入スケジュールと誰がどう運用するかを明記します。
これを入れないと「やるのは誰?」「ちゃんと回るの?」という不安が出てしまうんですね。
【導入スケジュール】 ・6月上旬:稟議通過後、業者へ正式発注 ・6月下旬:端末納品および初期設定完了 ・7月初旬:社内マニュアル配布・運用開始 ・7月中旬:初回フォローアップ(使用状況の確認) 【運用体制】 ・管理者:総務部 情報システム課 ・MDM管理:IT担当者が一元管理 ・使用者:営業部・マーケティング部を中心に順次展開
「計画的で、導入後もちゃんと回る」と感じてもらえるよう、細かく書いておくのがコツです。
なお、このテンプレートは業種・業態に応じて自由にアレンジできますので、状況に合わせて使ってくださいね。
まとめ|法人携帯 稟議・社内提案書の説得ポイント
| 提案書作成の要点まとめ |
|---|
| 提案書に必須の5つの構成要素 |
| 業務効率化と生産性アップの効果 |
| 「コストが高い」と言われた時の切り返し |
| 法人携帯プランの比較ポイント |
| 提案書テンプレートでの構成例 |
法人携帯の導入は、コスト面や業務改善、セキュリティ強化など、企業にとって多くのメリットをもたらします。
しかし、実際に導入へと進めるには、社内での稟議をクリアし、決裁者を納得させる提案力が欠かせません。
この記事でご紹介した内容を活用すれば、説得力のある提案書がスムーズに作成でき、稟議通過の確率もぐっと上がるはずです。
テンプレートや比較資料もぜひ活用して、あなたの提案を成功に導いてくださいね。
提案書作成や法人携帯選びで迷ったときは、一括.jpなどの一括見積サービスを活用するのもおすすめです。
さらに詳しく法人携帯の活用事例やセキュリティ対策について知りたい方は、以下の公的資料も参考になります。
この記事が、あなたの社内提案の成功と、法人携帯導入の第一歩に役立つことを願っています。

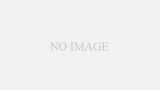
コメント